|
ペルシャ絨毯の基礎知識 目次へ
第4章 ペルシャ絨毯の主要産地
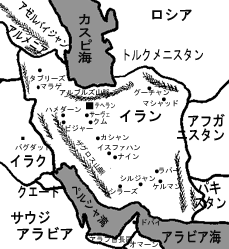
各産地では、デザイン、色使い、素材、織り方等、それぞれ違
った特徴のある絨毯が作られており、絨毯の名前は産地の地
名で呼ばれます。(遊牧民の絨毯やキリムは部族名で呼ばれる)
★ク ム(Ghom)
日本ではクムとかコムとかと云われていますが、イランでは
ゴームと呼ばれています。
クム(ゴーム)は、イランの首都テヘランの南約150kmにある
小さな町です。
イスラム革命の指導者ホメイニの出身地として名高く、マシャ
ッドに次ぐイラン第二の聖地として、イラン最大の神学校があ
り、聖職者(頭にターバンを巻いた独特の服装の人)を目に
する機会の多い町です。
近郊には塩の砂漠(塩湖)があり、塩分のきつい砂漠が取り
囲んでいます。従って、緑も少なく、おせじにも風光明媚とは
言えません。家並みも日干し煉瓦のため、茶色一色の世界です。しかし、この様な町で、あの華麗な
シルク絨毯が織られているのです。
クムは、現在では作られるほとんどの絨毯が100%シルク製というシルク絨毯の産地で、クムシルク
と言う様に『クム』と『シルク』は対にされて呼ばれ、シルク好きの日本人に広く知られています。
ここクムの絨毯の歴史は1930年位からと比較的浅く、それ故に「後進国の優位性」と言う言葉のよう
に、他の産地のデザインや技術、更にはペルシャ絨毯輸入国の好みを取り入れるなどして、急速に
発展を遂げてきました。(シルク絨毯を織るようになって40年位とのことです。)
特にシルク絨毯を好む日本人の『シンプル・イズ・ベスト』といえるような美意識に合わせた、色数が
少なくて淡い色使いの絨毯を作る工房が増えてきています。(一部では日本人が指定して作らせて
いるようですが、イランの固有の文化遺産・芸術を日本人が故意に変えてしまうようなことはどうでしょうか。)
そればかりでなく、踏んで使うとより白っぽく光ること、少しづつ日焼けもすることを考えると、あまり
に淡い色のものは避けたほうが良いと思います。
<補足>
日本で「クムシルク」として売られている絨毯の中には、本物の「クム」の他に「サーベ」「ザンジャン」「マラゲ」「ボナブ」など
で織られたシルク絨毯があります。
「サーベ」はテヘランとクムの中間位の西方にある町で、「クム」と同程度かそれ以上の品質のシルク絨毯を織っています。
代表的な工房としては「ラクシャニ」工房があります。サインはきちんと「サーベ・○○工房」と入れられており、高級品です。
「ザンジャン」はテヘランとタブリーズの間に位置する町で、シルク絨毯を織っています。品質は年々良くなり、20〜15年位前のクム以上の品質のシルク絨毯を織っているとはいえ、
現在のクムには及びません。「クム・○×工房」とサインが入れられているものがほとんどで、「クム」と称して売られていますが、クム産ではなくクムのコピー商品です。
「マラゲ」はタブリーズの南に位置する町で、やはりシルク絨毯を織っていますが、「ザンジャン」より更に品質は落ちます。
日本人バイヤーの希望により「クム・○×工房」とサインが入れられており、大型小売店を始め、ほとんどの絨毯屋が「クム」と称して堂々と売っています。
「ボナブ」産のシルク絨毯は問題外の品質ですが、最近「クムの特価品?!」として出回っており、百貨店
出入り業者も扱っているのを見掛けます。「特別奉仕品:クムシルク2×3m 90万円」などというのがその類です。
★イスファハン(Isfahan)
サファビー王朝時代の首都イスファハン(エスファハン)は、王朝時代の歴史的建造物が綺麗に保
存されています。町の中央にはザーヤンデ・ルード川が流れ、緑や公園も多く、風光明媚で、イラン
人も遠くから観光に訪れるなど、日本で言えば京都にあたる美しい古都です。
イマーム・モスクやシェイクロトフォラ・モスク、或いはアリ・カプ宮殿、チェヘル・ソトゥン宮殿などの壁
画やタイル、モザイクなどが今日においてもペルシャ絨毯のデザインの基となっています。
絨毯作りの歴史も古く、先に見てきたようにサファビー朝時代の名品も残されています。
イスファハンは、ウールの絨毯の産地ですが、細かな絨毯を織るために、縦糸に細くしても丈夫なシ
ルク糸を使うなど、高級ウール絨毯のみを作る産地として名を馳せており、名品、傑作が数多く作ら
れています。
日本人は着物文化の影響もあってか『シルク=高級』『ウール=安い』と思いがちで、(同じ位の価格
ならばシルク絨毯をと)ウール絨毯の中で比較的高価なイスファハン産の高級絨毯よりもマラゲ産の
安物のシルク絨毯が好まれる傾向にあるのは残念なことです。
★カシャン(Kashan)
 カシャンは、クムとイスファハンの中間に位置する古い町で、
カシャンは、クムとイスファハンの中間に位置する古い町で、
カシャンゲ(美しい)カシ(タイル)の町と言う所からその名が
ついたそうです。
カシャンはその気質の頑なさ故か閉鎖的なところがあり、街
並みも日干し煉瓦の上から泥を塗り固めた家がほとんど
で、田舎町の感があります。
でも、フィン・ガーデンの裏には絶える事のない綺麗な泉が
湧き出しており、風情があって静かな良い町です。
絨毯作りも頑固一徹で、モフタシェン・カシャンをはじめとした
アンティークの名品も多く生み出されています。
カシャンでは、およそ90%位がウールの絨毯を、10%位がシ
ルクの絨毯を生産しています。
クムに絨毯作りを指導した産地にもかかわらず、生産量、売
れ行きにおいてもクムに差をつけられている感がありますが、クムを凌駕する品質のシルク絨毯が
作られていることも確かです。
クムはタブリーズに習って、今日ではそのほとんどが、早く織れる鈎針を使って織られていますが、
カシャン絨毯は頑固に指でしっかりと織られ、高品質です。
イラン人はカシャン産の絨毯を『年老いてなお美人』と言い、古くなっても何時までも綺麗に使えると
珍重しています。
写真はカシャンの絨毯と7歳の少女、女性は7歳になるとチャドールを身に着けます。家の中では黒ではなく
この様な白地に花柄のものがよく使われています。(ちなみに、首都テヘランでは家の中では普通の洋服、
外出時にはロングコートにスカーフという人が多いようです。)
最近クムで鈎針を使って織った「カシャン」やマラゲ産のコピー商品が結構出てきています。
★ナイン(Nain)
ナイン(ナイーン)はイスファハンに近い小さな町で、ウールをベースにして、文様の縁取りに少しシル
クを使った絨毯を織る産地です。
ナインでの絨毯作りの歴史は比較的浅く、かつては羊の毛を押し固めたフェルトでつくる、ペルシア
独特の外套のような衣服の産地だったそうです。
しかし、近年イランでも、西洋式の衣服が用いられるようになり、そうした産業は衰退して、1920年頃
から絨毯作りによって生計を立ててきたと言われています。
ナインでは、絨毯の技術がイスファハンから伝えられたことから、今もシャー・アッバス・メダリオン・
コーナー・デザインの絨毯が最も多く作られており、細かい方とやや粗い方というように2種類の品
質のほぼ均等の絨毯が織られているのが特徴です。
また、ベージュやクリーム色をベースにした大人しい色使いから、日本家屋に合わせ易いので、日
本でも人気があります。
近年、素材、織共に品質の落ちるタバス産のナインのコピー商品が日本で大量に売られています。
タバス産の「ナイン・ハビビアン工房」とサインの入った絨毯が多いのには驚かされます。(これも日本のイラン人絨毯屋及び日本人絨毯屋が流行らせたのです。)
また、カシュマル産のものを「ナインの特価品」として販売しているのも見受けられます。「信用第一」の百貨店も例外ではありません。
★タブリーズ(Tabriz)
タブリーズ(タブリッツ)はイランの北西に位置し、トルコやヨーロッパに近いと言う地理的な条件か
ら、古くからシルクロードの交易の拠点として栄えた商業都市です。
しかし、交易で栄える町は侵略に晒されるのが常で、タブリーズもまたトルコの支配下で栄えた時期
の方が長い位です。
そうしたことは、タブリーズで今も日常は、ペルシャ語ではなくトルコ語を使っている人が多いことにも
示されています。
絨毯は、リーズマヒ(小さな魚)と呼ばれるトラディショナルなデザインのもの、ピンク・ベージュ系のメ
ダリオン絨毯、絵画絨毯等幅広く作られています。
タブリーズ産の絨毯も、ウールがベースですが、中には、3〜5色位のシルク糸を花の所に使って、
華やかに仕上げたものもあり、イスファハンやナイン同様ウールにシルクを織りまぜて絨毯を作る産
地です。また、ナイフの先に鈎針の付いた道具を駆使して織るため、織るスピードが速く、生産量も
豊富です。
★ケルマン(Kerman)
2003年の地震で倒壊したケルマン州バムの町の要塞『アルゲ・バム』は、遠くササン朝ペルシアの
時代に作られたものでした。このことからもわかるように、ケルマン州の州都ケルマンは古い歴史を
持つ町で、テヘランの南東約1,000キロ強のルート砂漠の高地にあります。
かつてケルマン(ケルマーン)は、刺繍が有名で、刺繍を施したショールがヨーロッパの貴婦人にも
てはやされた(18世紀頃)そうですが、19世紀頃から、そのショールの衰退と共に、ショールのデザイ
ンを生かした絨毯を盛んに作るようになったと言われています。
現在、博物館となっているイランの宮殿には、古いケルマン産の絨毯の名品が数多く敷かれてお
り、今日では、フランス風の花柄の特徴あるウール100%の絨毯が織られています。
また、ケルマンでは糸に紡ぐ前の原毛の段階で染める(先染め)ため、毛の芯までしっかりと染め上
げられていることから、絨毯が古くなっても色あせしにくく、素晴らしい色になっていくことでも知られ
ています。
中でも、ケルマンの町から北西140キロほどにあるラバー村は、最高のケルマン絨毯を作っているこ
とで有名で、一般的なケルマンと区別してケルマン・ラバーと特定して呼ばれています。
イランには、町や村の数だけ産地があると言って良い程ですが、他の産地についてはまたの機会に
譲ります。ギャベというのは産地名ではなく毛足の長い絨毯のことです。シラーズ近郊のザグロス山
脈の麓で遊牧生活を送っているカシュガイ族などが織っています。(今日では工房で織っているもの
が殆どですが。)
尚、カシャンのウール絨毯のコピー絨毯を織る産地では、「ヤズド」、ナインのコピー絨毯を織る産地には「タバス」「カシュマ
ル」、タブリーズのコピー絨毯を織る産地には「ホイ」などがあります。
但し、「ホイ」産の絨毯はタブリーズ産のコピー絨毯で、当然タブリーズ絨毯より品質が劣るのですが、タブリーズ以上の品
質の絨毯を織る工房が一つだけ存在しています。
第5章 ペルシャ絨毯のサイズへ進む
このページのTopに戻る
ペルシャ絨毯の基礎知識 目次へ
Copyright 趣味人の悦楽 All Rights Reserved
|
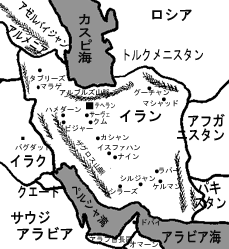
 カシャンは、クムとイスファハンの中間に位置する古い町で、
カシャンは、クムとイスファハンの中間に位置する古い町で、